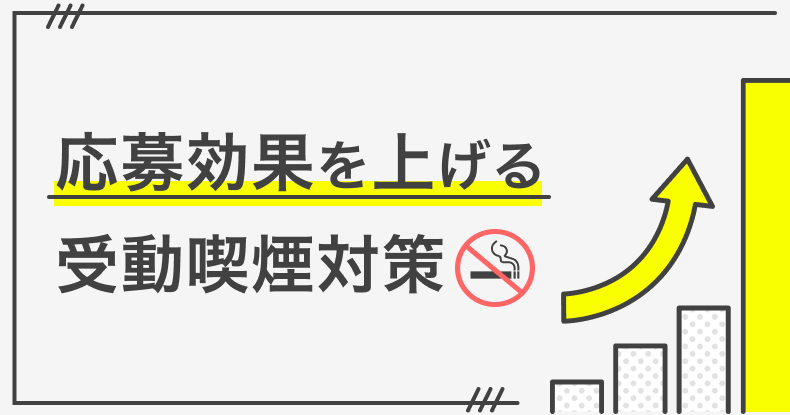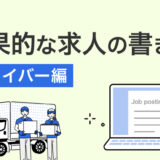2020年4月1日に改正された「健康増進法」によって、受動喫煙対策に対応した求人へと書き方を変更することが義務付けられました。しかし、「受動喫煙対策としてとりあえず記載している」「喫煙者は応募NGにしたいけれど、求人への書き方がわからない」そんなお悩みを抱えるご担当者様も非常に多いはずです。
本記事では効果的な求人の書き方にお悩みの方に向けて、受動喫煙対策に対応した求人への記載方法を解説します。
受動喫煙対策とは
まずは、受動喫煙対策とはどんな内容を指すのか、法の具体的な概要や求人への書き方の注意点を解説します。
「健康増進法」改正により求人記載が義務化
受動喫煙対策とは、2020年4月1日に改正された「健康増進法」によって施行された、望まない受動喫煙を防止することを目的とした取り組みです。2019年1月から段階的な施行が開始となり、2020年4月には対象となる施設での敷地内禁煙や、屋内禁煙(喫煙専用室などの設置)などを含む全面施行となりました。
そして本法改正に伴い、受動喫煙対策に関する内容を求人に明示することも義務付けられました。きちんと記載することで従業員の受動喫煙を防ぎ、求職者に必要な情報を開示することが事業者の大切な役目です。書き方次第では採用にも影響することがあるため、本記事を参考に適切な明示方法を理解していきましょう。
求人に受動喫煙対策を明示する際の注意点
受動喫煙対策を求人へ明示する際の注意点は以下の4点です。
- 実際の就業場所においての受動喫煙対策を明示すること。
- 複数の就業場所での勤務が予定されている場合は、それぞれの就業場所においての受動喫煙対策を明示すること。(※出張や転勤は除く)
- ドライバー乗務員など移動が必要な業務は、立ち寄る場所と業務場所、それぞれの対策状況を明示すること。
- 喫煙可能区域で勤務する業務には、20歳以上の人材を採用すること。(※求人へ記載する年齢制限事由は「健康増進法により20歳未満立入禁止のため」と記載)
参考:厚生労働省|受動喫煙リーフレット
受動喫煙対策を求人に明示しなかった場合の罰則
受動喫煙対策を求人に明示することは義務付けられているため、記載しなかった場合は法令違反に伴う罰則が課せられます。最初は指導が中心ですが、それでも義務違反が継続する場合は勧告・命令等を行い、最終的には違反内容ごとに罰則(過料)が適用になることが一般的です。あわせて、ハローワークなどでの求人公開や職業紹介の利用もできなくなります。
受動喫煙対策で応募効果が変わる?
受動喫煙対策を行えば応募効果は変わるのでしょうか? ここからは、受動喫煙対策がもたらす応募効果への影響を解説します。
書き方次第では、応募効果向上も可能
受動喫煙対策はもちろんのこと、それ以外の法対応やメリットの表現方法などにおいても書き方次第では応募効果の向上が可能です。まずは正しく書くことが大切ですが、そのうえで求職者が読みやすい位置に、端的に記載することで応募を集めやすくなります。「定型でとりあえず入れ込めばいい」ではなく、求職者の目線で分かりやすい表記を心がけましょう。
書き方に不安がある場合は、求人のプロに相談
受動喫煙対策をはじめとした法に関する記載や、求人自体の書き方に不安がある場合は、求人の知識が豊富な採用のプロに任せることも良策です。たとえば、弊社が提供する採用管理システム(ATS)アットカンパニーであれば、最新の法に対応した記載方法はもちろん、効果的な求人作成のアドバイスなども受けることができます。幅広い職種や業種にも対応していますので、法対応に自信がない場合などは、ぜひアットカンパニーの活用をご検討ください。
受動喫煙対策に対応した求人の書き方
ここからは、受動喫煙対策に対応した求人を書くうえでの、具体的なポイントについて解説します。
受動喫煙対策はほぼすべての業種で必須
受動喫煙対策に対応した求人記載は、ほぼすべての業種が対象となります。健康増進法によって定められている喫煙スペースの設置などの措置については、一部バーやスナックなど喫煙を目的とした業種は免除されていますが、求人への記載は同様に義務付けられています。記載すべき内容を理解したうえで、分かりやすく記載することを心がけましょう。
受動喫煙対策に対応した求人への記載内容
受動喫煙対策に対応した求人への記載内容は、以下のとおりです。求人への記載が必要な内容は就業場所などによって異なるため、該当する項目を参考にしてください。
たとえば、一般企業で喫煙室(喫煙目的室)を設けており、受動喫煙対策に対応している場合は、「受動喫煙対策あり/喫煙専用室設置」のように記載します。実態が伴っていないと法令違反となることはもちろん、採用に至っても早期退職の原因となることがほとんどです。求人に記載する際には、組織内の受動喫煙対策ができていることを確認しておきましょう。
喫煙者の採用を避けたい場合の求人の書き方
喫煙者の採用を避けたい場合は、応募条件として記載してもよいという考え方が多くありますが、法令などでは明文化されていない状況です。
厚生労働省が採用選考に関しての考え方をまとめた公正採用選考サイトでは「職務を遂行するために必要な適性・能力以外の要素を応募条件としない」という方針が示されていますが、一方で受動喫煙対策によって労働者を守る方針を打ち出しています。
これらの方針を踏まえると、組織内に喫煙場所を作らず、全面禁煙であることを求人内に記載する方法が良策です。応募条件として明記しなくても喫煙者の応募を避けることができ、法令に触れる心配もありません。全面禁煙をアピールポイントとして表現することで、ターゲットを絞った求人が可能になるでしょう。
受動喫煙対策の記載によって得られるメリット
受動喫煙対策の求人記載は手間のかかる作業ですが、記載することで得られるメリットもあります。最後に受動喫煙対策の記載によって得られる代表的なメリットを解説します。
働きやすい環境をアピールできる
受動喫煙対策を求人に明記することで、求職者にとって働きやすい整った労働環境であることをアピールできます。とくにタバコが苦手な求職者や健康志向の高い求職者にとっては、職場を選ぶうえでの重要な指標になるポイントです。またそのほかの求職者に対しても整った労働環境であることをイメージづけられるため、よい組織であることのアピール材料になります。
健康にも配慮している姿勢を表現できる
受動喫煙対策を求人に明記することで、社員の健康にも配慮している企業姿勢を表現できます。求職者が応募先を決める際には、福利厚生や待遇なども企業選びの指標になりますが、待遇などを通して「社員を大切にする企業か」ということにも注目しています。
そのため、組織としての受動喫煙対策を明らかにし、求職者に安心感を与えることは重要です。長く働き続けたい求職者ほど、安心して働ける労働環境を求めるため、できるだけ分かりやすく表記しておくことをおすすめします。
応募数をUPする効果も
受動喫煙対策を求人に明記することで、応募数のUPにつながる場合もあります。たとえば、先程解説した「働きやすい環境であること」や「社員を大切にする企業であること」を上手くアピールできるだけでも、応募数を集めやすくなるものです。法に基づいた表記以外に、社員や働く環境を大切にしている旨を表記すれば、より応募効果を高めることができます。
受動喫煙に関する表記は法令を順守する必要がありますが、法令への対応を上手く利用した求人でのアピールも可能です。受動喫煙対策として禁煙、または分煙などの対応を選択した意図などを書き入れるのも、組織の方針や雰囲気を伝える材料となります。求職者が安心して応募に至り活躍できるよう、法令を理解したうえで効果的な求人作成を目指しましょう。
まとめ:受動喫煙対策を理解しより効果的な求人作成を
本記事では効果的な求人の書き方にお悩みの方に向けて、受動喫煙対策に対応した求人の記載方法を解説しました。法令を順守した記載はもちろん大切ですが、「とりあえず法令にあわせて定型で記載しておく」のはもったいない部分もあります。この機会に求人内容を再度チェックし、効果的な求人表現へ改善を図ってみることをおすすめします。
また、法令対応に不安がある場合やより効果的な求人にしたい場合は、記事内でもご紹介した採用管理システム(ATS) アットカンパニーの利用も良策です。求人のプロである専任のサポートを受けながら、法対応と効果的な募集を同時に実現できます。自社の採用力UPをお考えの場合は、ぜひこの機会に、アットカンパニーの利用をご検討ください。詳細なサービス内容については下記ボタンよりご覧ください。