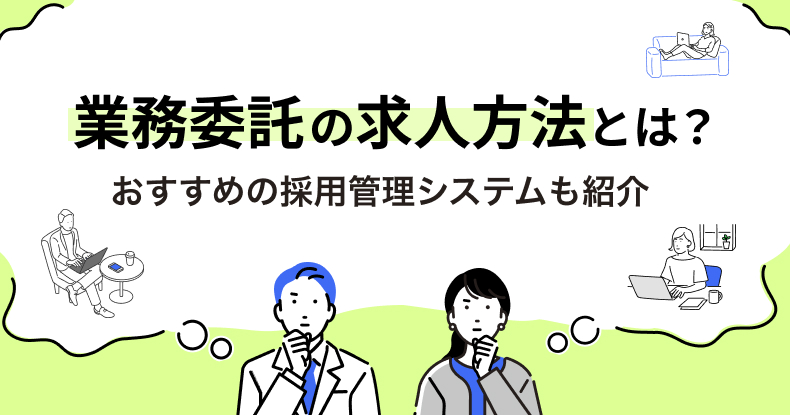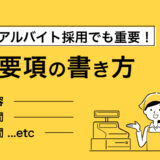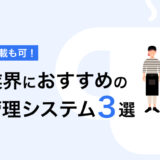近年、ビジネスシーンでは業務委託人材を積極的に活用する企業が増えています。業務委託を活用することで、専門性の確保や人材採用・育成の効率化を図ることが可能です。
しかし、業務委託はメリットばかりではなくデメリットも存在するため、活用を検討する際は、慎重に進める必要があります。本記事では、業務委託の基本から具体的な採用方法、おすすめの採用管理システム(ATS)まで解説しますので、ぜひご参考にしてください。
目次
業務委託とは? ほかの契約との違い
業務委託は、企業が自社の業務を外部の個人や企業に委託する形態です。ここでは、業務委託契約の基本と、雇用契約および派遣契約との主な違いを解説します。
業務委託とは
業務委託とは、特定の業務を外部の個人または企業に委託し、その業務の遂行に対し報酬を支払う契約形態です。委託される業務には、具体的な成果が求められるため、契約内容には業務の範囲、期限、報酬などが詳細に定められます。
また、業務委託は企業と雇用関係がないため、労働基準法などは適用されません。したがって、受託者側は業務の遂行方法に関する指示は基本的にはなく、いつ、どこで働くかは自身の裁量に委ねられ、自由な働き方が可能です。
一般的にはフリーランスや個人事業主が、企業と業務委託を結ぶケースが多くなっています。業務委託が多く採用されている職種例としては次のとおりです。
- デザイナー
- プログラマー
- システムエンジニア
- ライター
- イラストレーター
- コンサルタント
- 営業
- ドライバー
- エステティシャン
- 医者
- 弁護士、税理士など
雇用契約との違い
雇用契約では、雇用者と従業員との間に法律的な雇用関係が結ばれます。雇用者は、従業員に対して給与を支払う代わりに、従業員から労働力の提供を受けます。
雇用契約は労働基準法の適用を受けるため、労働時間、休日、などの労働条件が規定されています。また、雇用契約では雇用者が従業員に対して指揮命令権を持ち、従業員はその指示に従う必要があります。
一方、業務委託契約では、受託者は特定の成果物やサービスを提供する責任を持ちますが、その遂行方法については自由に決定できる場合が多く、労働時間や場所についても柔軟性があることが特徴です。
派遣契約との違い
派遣契約は、派遣社員を雇用する「派遣元企業」と、派遣社員を受け入れる「派遣先企業」との間で結ばれる契約形態です。
この形態では、派遣元が派遣社員に対して使用者責任を持ち、給与や労働条件を提示します。また、業務の指揮命令権は派遣先にあり、派遣先は派遣社員に対して日常的な業務の遂行に必要な指示を行うことが特徴です。
一方、業務委託では、受託者または受託企業が独立して業務を遂行し、成果物やサービスの提供を行うといった違いがあります。
業務委託の種類
業務委託は、「請負契約」と「委任/準委任契約」のふたつに分類され、総称として業務委託契約と呼ばれます。これらは法律上の扱いや業務遂行における責任の所在が異なるため、適切な契約形態を選択することが重要です。それぞれの契約形態の違いを詳しくみていきましょう。
請負契約
請負契約は、成果物の提供を目的とした業務委託契約です。この契約では、受託者は定められた期間内に特定の成果物を完成させ、提供する責任を負います。報酬は成果物が委託者の要求基準を満たした時点で支払われることが一般的です。
たとえば、WEBライターの記事執筆やWEBサイトの開発などが挙げられます。請負契約では、仕事の品質や成果物に対する責任が受託者にあるため、不備や不具合があった場合は修正義務が発生します。
委任(準委任)契約
委任契約は、成果物の提供ではなく、業務遂行そのものを目的とした契約形態です。委託契約は、業務の遂行過程における労働の提供にもとづいて支払われます。
委任契約では成果物の完成を保証する責任は原則として受託者にはありませんが、受託者は業務上必要なコミュニケーションや物品の取り扱いを適切に行う、いわゆる「善管注意義務」を果たす必要があります。
委任契約の例としては、弁護士や税理士のような士業や、経営コンサルタントなど専門職による相談業務があります。委任契約では、具体的な作業プロセスが重視されるため、業務への対応力や品質が直接的な報酬に影響します。
企業で業務委託の活用が注目される理由
近年、企業では業務委託人材を活用するケースが増えています。株式会社みらいワークスが実施した「企業の業務委託利用」に関する実態調査では、83.4%の企業が今後プロ人材の業務委託が必要になると回答しています。
この数値からも、企業における社内でのプロ人材の育成が困難になっていることや、企業は新規事業の推進や事業変革に対応するために外部の専門家の力を求めていることがわかります。また、直接的に利益を生み出さないものの、業務の遂行を後押しする「ノンコア業務」を外部に委託することで、人件費の削減や業務効率化を図る企業も少なくありません。
とくに、市場の動向や技術の進展スピードが早い現代では、プロジェクトの進展にあわせて高い専門性を持つ人材を素早く確保することが重視されています。このように、企業戦略の柔軟性と効率性を高める有効な手段として、業務委託人材の活用は一層重要といえるでしょう。
業務委託を活用するメリット
業務委託を活用することは、企業にとって多くの利点をもたらします。ここでは業務委託を活用するメリットを詳しく解説します。
社内リソースを別の業務にあてられる
業務委託を活用することで、社内リソースをより生産的な活動に集中できます。たとえば、日常的な運用や管理業務を外部に委託すれば、社内のスタッフは新しいプロジェクト開発や戦略的なタスクに専念できるでしょう。
これにより、既存社員をより重要な業務に割りあてることができ、企業全体の生産性が向上し、事業の成長と効率化が促進されます。
必要なときにだけ仕事を依頼できる
業務委託は、必要に応じて専門的な作業を委託できる柔軟性を企業に提供します。特定のプロジェクトや繁忙期にのみ外部の人材を利用し、恒常的な人件費の負担を避けることができます。
事業の変動に柔軟に対応する能力が高まり、不要時にはコスト削減ができ経済的です。
教育の手間がかからない
新たなスキルや専門知識が必要な業務を社内で行おうとすると、従業員のトレーニングと教育に多大な時間とコストがかかります。
しかし、業務委託を利用すれば、外部の専門家に任せることができるため、教育に関連する時間とコストを節約でき、比較的短期間で業務の成果を得られます。
専門性が高い業務を任せられる
一般的に、特定の専門分野で高い技能を持つプロ人材は希少価値が高く、これらの人材を常時雇用するのはコストが高くなります。業務委託を利用することで、企業は特定の専門知識を持つ人材をプロジェクトベースで活用できます。
これにより、高度な技術や専門的な知識が求められる業務に対応できるようになり、自社製品やサービスの品質向上に寄与します。
業務委託を活用するデメリット
業務委託の活用には多くのメリットが得られる一方、いくつかのデメリットも存在します。企業が業務委託を新たに活用する場合は、デメリットを念頭に置きつつ、戦略的に活用することが大切です。
ここでは、業務委託の主なデメリットを詳しくみていきましょう。
社内にノウハウが蓄積しにくい
業務委託のデメリットのひとつは、企業内に専門的なノウハウや知識が蓄積されにくいことです。外部の専門家に業務を依頼すると、そのプロセスや専門知識が社内に根付かず、外部依存が強まる可能性があります。
また、長期的にみると、企業が自力で問題を解決する能力を低下させる可能性があり、市場内での競争優位性の低下や成長スピードの遅れにもつながります。
業務内容によってコストが高くなる可能性がある
業務委託は、社員の人件費削減にも有効ですが、企業トータルでみた場合、必ずしもコスト削減につながるわけではありません。とくに専門性が高い業務を外部に委託する場合、外注コストは当初の想定以上に高額になるケースもあります。
委託する業務の内容や難易度、市場での専門家の需要と供給によっては、内部で行うよりも高額な費用が発生する場合も考えられます。したがって、誰に、何を、いくらで依頼しているかがリアルタイムで把握できるように、業務委託人材を適切に管理することが重要です。
委託する人によって能力や成果に差がある
一般的に業務委託はフリーランスや個人事業主などの、特定の個人に仕事を依頼するケースが多くなります。しかし、こうした個人は専門家といえど、スキルや能力が異なり、成果物の品質にも大きなばらつきがあります。
したがって、委託先によっては期待した成果が得られないリスクがあります。このような不確実性は、プロジェクトの成功に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
直接雇用と比べると、帰属意識が高まりにくい
業務委託はあくまで専門範囲内での業務遂行に専念し、その対価として報酬を受け取るという働き方のため、特定の企業に対し帰属意識を持つことが難しい場合があります。
とくに業務委託で働く人々は、自己のスキルや専門性を生かして複数の案件をこなしています。その結果、特定の企業に対する帰属意識やロイヤリティは持ちにくくなります。
一方、社員など直接雇用の場合は企業のミッションやビジョンに共感し、企業の変化に柔軟に応じることが求められるため、より強い帰属意識を持つことが一般的です。
したがって、業務委託はスキルや特定の機能を求める際には有効ですが、企業の文化やミッションの実現には直接雇用による社員の育成が重要となります。
業務委託人材を活用する際の注意点
業務委託人材を効果的に活用するためには、注意が必要です。これらに対処することで、業務委託のリスクを抑えつつ、そのメリットを最大限に引き出すことが可能です。
機密情報漏えいのリスクがある
業務委託では、機密情報漏えいのリスクが常に存在します。契約の際、多くの企業が業務委託契約書や秘密保持契約(NDA)を交わすものの、稼働状況を細かくチェックすることは難しいのが現実です。
さらに、契約終了後に業務委託人材が保有する機密情報が適切に破棄したかどうかを確認することも容易ではありません。このため、重要な情報の取り扱いにはとくに注意が必要であり、データのアクセス権限を厳格に管理し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
必要なときにコミュニケーションが取れない可能性がある
業務委託人材は自由な働き方をするため、いつ・どこで・どのように仕事をしているかを常に把握することは困難です。とくに成果物に対してのみ報酬を支払う請負契約の場合、稼働時間を指定すると抵抗感を示される可能性があります。
基本的な連絡手段としてはチャットやメールを活用することになりますが、人によって返信のタイミングも異なるため、円滑なコミュニケーションが難しいと感じる場合があります。この問題を解決するためには、稼働開始のタイミングでキックオフミーティングを設けたり、定期的にミーティングを実施したりして、業務ルールの伝達やフィードバックを行うことが効果的です。
業務委託人材を集める方法
業務委託人材は、企業の柔軟性と専門性を高めるうえで貴重な戦力です。しかし、自社にとって適切な人材を見つけるためには、どのような方法があるのでしょうか? ここでは、業務委託人材を集める主な方法を4つご紹介します。
自社の採用ホームページで募集する
自社の採用ホームページを活用することで業務委託人材を集めることができます。この手法の主なメリットは、自社の強みや魅力、価値観をより詳しく伝えられる点です。代表インタビューや社内コラム、動画コンテンツなどを発信し、他社との差別化を図ることができます。
候補者は応募の段階で、企業に対してある程度の理解を持つため、より質の高い人材が集まりやすいという利点があります。
また、自社の採用ホームページの情報を最適化することで、Indeedや求人ボックスなどの求人検索エンジンに自動で読み込まれ、費用をかけずとも自社の募集情報を発信することが可能になります。
▼業務委託のIndeed掲載については、こちらの記事で詳しく解説しています
 Indeedで派遣や業務委託の求人は掲載されない? 注意点や打開策を考察
Indeedで派遣や業務委託の求人は掲載されない? 注意点や打開策を考察
求人サイトで募集する
業務委託人材を集める際は、求人サイトを利用することで、より多くの候補者に対しアプローチできます。求人サイトの種類は多岐に渡り、大手人材会社が運営する人気サイトから、業界や業種に特化したニッチなサイトまでさまざまです。
また、求人サイトを利用することで、広告の出稿から応募者の管理まで、多くの工程を自動化できるため、採用プロセスを効率的に進めることができます。ただし、広告料金や利用料が発生するため、コストを考慮する必要があります。
クラウドソーシングで募集する
クラウドソーシングとは、特定の業務を依頼したい企業と、仕事を受けたい個人をマッチングするオンラインサービスです。
クラウドソーシングプラットフォームには、自身のスキルや専門性を活かして働きたいフリーランスや個人事業主、副業人材など数多くの人材が登録しています。とくに一時的またはプロジェクトベースの仕事に適しています。
クラウドソーシングを利用することで、短期間で多数の候補者から提案を受け取り、最適な人材を選択することができます。しかし、多くのクラウドソーシングはオンラインベースで働くことを条件としており、対面でのコミュニケーションが禁止されている場合もあります。
したがって、業務委託人材との適切なコミュニケーションやプロジェクトの進捗管理には注意が必要です。
従業員や知人に紹介してもらう(リファラル採用)
従業員や知人から人材を紹介してもらう方法(リファラル採用)も有効です。業務の性質や企業文化への適合性をある程度保証された形で人材を確保できる点が大きなメリットといえます。
また、紹介による採用であるため、採用コストの削減にもつながります。ただし、限られたネットワーク内でのみ候補者を探すため、母集団の獲得や人材の多様性に欠ける可能性もあります。
業務委託の採用に強い採用管理システム(ATS)
業務委託を効率的に採用するためには採用管理システム(ATS)の導入が欠かせません。採用管理システム(ATS)を導入することで、採用進捗の可視化やデータにもとづいた分析・改善、スピーディな求人掲載など、さまざまな機能を活用できます。ここでは、各システムの概要と業務委託の採用に役立つポイントを詳しくご紹介します。
アットカンパニー

アットカンパニーは、求人広告の経験豊富な専任スタッフが支援する採用管理システム(ATS)です。このシステムは、採用ページの作成や求人配信、応募選考管理、WEB面接機能など、採用活動をトータルでサポートします。
とくに業務委託の採用においては、Indeedなどの求人検索エンジンでの実績をもっており、有料オプションを利用することでIndeed検索結果の上位に表示させることが可能です。
- 求人検索エンジンとの連携:Indeedなどの大手求人検索エンジンに対応し、有料オプションを利用することでIndeed検索上位に表示することが可能
- 専門人材によるサポート:採用ホームページや求人ページの作成・運用を専任スタッフがサポートするため、採用活動の手間が省ける
より詳しいプランの内容につきましては、下記ボタンより資料をご覧ください。
Workship ENTERPRISE

Workship ENTERPRISEは、フリーランスや副業人材の採用を専門とするプラットフォームです。51,000人以上のフリーランスが登録しており、職種やスキルに基づいて候補者を検索し、直接アプローチが可能です。
これにより、業務委託で求められる多様なニーズに迅速に対応することができます。また、低コストでの採用が可能であり、成果報酬型の料金体系も採用コストの削減に貢献します。
- フリーランス採用に特化:51,000人以上のフリーランスが登録しており、職種やスキルで直接検索しアプローチが可能
- 採用時にのみ費用が発生:利用料金は成果報酬型なので、採用活動費抑えながらハイスキル人材を採用できる
エクスチーム

エクスチームは、業務委託契約に特化したフリーランス管理プラットフォームです。発注から納品、請求までの全プロセスをオンラインで一元管理し、業務委託の法令対策にも対応します。
このシステムは、発注漏れや契約書紛失を防ぎながら、フリーランスからの請求書発行も自動化します。これにより、業務委託の運用を効率化し、企業とフリーランス双方の時間と労力を大幅に節約できます。
- 業務委託契約を一元管理:発注から納品、請求までの全プロセスをオンラインで一元管理し、業務委託の法令対策にも対応
- 契約書類の管理・発行にも対応:契約書管理や請求書発行まで自動化し、運用効率を大幅に向上させる
まとめ:業務委託を活用して自社の専門性を高めましょう!
業務委託人材を活用することで、社内リソースの最適化や育成コストの削減が可能です。また、市場の変化が早い現代のビジネスシーンにおいて、企業は新規事業の推進や事業変革に対応するために、高い専門性を持つ業務委託人材の活用が一層求められています。
一方、業務委託はあくまで外部人材であり、タスクの遂行に対して報酬を支払う契約形態です。したがって、契約の際は業務委託契約書や機密保持契約(NDA)の取り交わしはもちろん、依頼案件の進捗確認が欠かせません。
業務委託人材を効率的に採用・管理するためには、クラウドソーシングや採用管理システム(ATS)の活用がおすすめです。業務委託人材の効率的な活用を実現するために、自社にあったサービスの導入をご検討ください。
求人のプロがついた採用管理システム(ATS)アットカンパニーなら業務委託の採用実績も多数!豊富な経験とノウハウで貴社の採用活動を徹底サポートいたします。アットカンパニーのことが3分でわかるサービス資料はこちらから