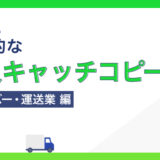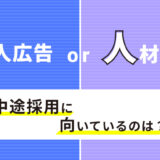求人ボックスは、2025年6月現在の月間利用者数は1,137万人と、国内トップクラスのユーザー数・求人数を誇っています。知名度も高く、評判のよい求人ボックスですが、実際利用するにあたってデメリットもしっかりと把握しておきたいところです。メリットやデメリットを補う方法も含めて、この機会に理解しておきましょう。
今回は、求人ボックスの仕組みや特徴とともに、利用する際のデメリットや対策方法を解説します。
目次
求人ボックスの仕組みや特徴
求人ボックスのデメリットを理解するために、求人ボックスの基本情報の把握が必要です。まずは求人ボックスの仕組みや特徴について確認していきましょう。
求人ボックスの仕組み
求人ボックスは、求人情報の一括検索サービスです。企業が求人ボックスに掲載する方法は主に2種類あり、求人ボックス内で直接求人情報を入力し掲載する「直接投稿」と、ほかの求人サイトや企業の求人ページなどから一定の条件に従って求人情報を自動で収集する「クローリング掲載」があります。
2,000万件以上もの豊富な情報を閲覧できるのは、直接投稿されたものに加え、クローリング掲載によってほかのサイトから収集した求人情報もあわせて掲載されているためです。求職者にとっても、複数のサイトの情報をまとめて閲覧できることが高い利便性につながっており、年々ユーザー数を伸ばし続けています。
クローリングについてはこちらの記事をご参考にしてください。
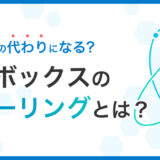 求人ボックスのクローリングサービスはIndeedの代わりになる? 仕組みや注意点を解説
求人ボックスのクローリングサービスはIndeedの代わりになる? 仕組みや注意点を解説
求人ボックスの主な特徴
求人ボックスは、郊外地域の採用にも強いなどさまざまな特徴がありますが、もっとも大きな特徴は無料掲載ができる点です。一般的な求人サイトに比べ掲載の費用を抑えられるうえ、簡単な手続きのみで多くのユーザーにリーチできることは、求人ボックスがもつ大きな特徴だといえます。
また、無料掲載で効果が出ない場合や、急ぎで採用が必要な場合には、有料掲載で露出を高めることも可能です。費用はクリックされるごとに発生する「クリック課金」方式となっており、無駄な費用をかけずに求人効果を高められます。採用方針や状況に合わせて、最適な方法で利用を始められるでしょう。
求人ボックスのデメリット
ここでは、代表的なデメリットを理解しておきましょう。
求人を自社で作成する必要がある
求人ボックスを利用する際には、求人を自社で作成する必要があります。求人に記載すべき要件や情報を整理し、掲載規定に従って求人を書くことにも注意しましょう。求人作成の経験がなければ、掲載規定を踏まえて、正確な情報を求人に落とし込むだけでも苦労する場合があります。掲載の続きも含めると、比較的多くのリソースを割く可能性があることを、理解しておくことが大切です。
また、応募数を担保するために、ターゲットに向けた効果的な求人を作成することも求められます。求人や採用の知見のある人物であれば問題ありませんが、初めて作成する場合は、ある程度のトライアンドエラーが必要な場合がほとんどです。社内のリソースに合わせて、効果が出るまでの期間を長めに見積もっておくことをおすすめします。
運用の知識がないと効果が出にくい
求人ボックスの利用にあたり、求人運用のノウハウが社内にない場合は、効果が出にくいこともあります。運用で必要になるのは、求人の表示回数・クリック数・応募率・面接率などを分析し、必要に応じて求人原稿自体や採用選考フローなどを調整することです。とくに課題に対して適切な改善をおこなうには、一定の知識や経験が必要となることを理解しておきましょう。
また、運用に多くの手間がかかるため、人員や作業コストが発生することも理解しておく必要があります。求人の知識やデータ分析の知見がある人材を配置するなど、効果的な運用を行うための体制づくりが非常に大切です。
有料オプションにも手間と費用がかかる
求人ボックスの有料オプションを利用する場合は、運用の手間と費用がかかります。無料掲載で効果がでなければ、有料掲載で露出を高めることも可能ですが、有料プランの運用にはある程度の知識が必要です。
費用はクリックされるごとに発生する「クリック課金」方式であるため、状況把握やキーワード選定などの判断が求められます。クリック単価は求人広告の品質などによって変動するため、最初の内は思ったような費用対効果が得られない場合もあるでしょう。
Indeedに比べて効果が出にくい
国内トップクラスのユーザー数を誇る求人ボックスですが、Indeedに比べ効果が出にくい場合があります。効果の差が生まれる理由としては、ユーザー数に大きな違いがあるためです。
求人ボックスの月間利用者数は1,000万人以上ですが、その2倍以上の利用者をIndeedは取り込んでいます。運用次第では効果を出すことも可能ですが、ターゲットに合わせた求人原稿の作成など、応募を集めるための工夫も必要になるでしょう。
求人ボックスのメリット
求人ボックスには、デメリットを補うメリットがあります。ここでは、求人ボックスの代表的なメリットを解説します。
無料掲載が可能
求人ボックスは無料掲載ができるため、費用を抑えた求人が可能です。採用に至った場合も費用は一切発生しないので、計画的に採用活動が行えます。従来の有料求人広告や人材紹介などの場合は、数十万〜数百万円のコストがかかるのが一般的です。求人ボックスの無料掲載で採用できれば、これらの費用をかけることなく人員を増やせます。求人ボックスの無料掲載は、事業運営の大きな助けとなるでしょう。
期間の制限がない
求人ボックスは求人掲載に期間の制限がないため、長く求人を出し続けられます。もちろん掲載開始から期間に応じて掲載順位は下がりますが、定期的に情報を更新すれば掲載順位の低下を防ぐことも可能です。一度掲載手続きをすれば、修正や更新もすべてオンライン上で完結するため、求人掲載ごとの手間が少ないのも大きなメリットです。効果的な求人作成や運用のコツを理解すれば、効率よく効果的な求人を行えます。
マッチングしやすい検索機能
求人ボックスでは、有料で利用できる「ユーザー属性別ターゲティング機能」によって、マッチング率の向上が期待できます。ユーザー属性別ターゲティング機能とは、性別や年代に絞って求人を配信できる機能です。必要なターゲットに情報を届けられるため、クリック単価を効果的に使うことができます。
また、ターゲット以外への配信を除外する「配信対象外検索キーワード」を設定すれば、無駄なクリックを防ぐことも可能です。限定したターゲットに絞って費用を使えるため、運用次第ではマッチング率を高める効果を期待できるでしょう。
求人ボックスのデメリットを補う方法
求人ボックスの「求人を自社で作成する必要がある」「運用に知識や経験が必要」といったデメリットは、対策をすれば簡単に補えます。効果的な運用にもつながる方法ですので、ぜひこの機会に対策方法を理解しておきましょう。
社内に専任の担当者を配置する
求人に関する知識や経験のある人材に求人の作成など採用活動の一端を任せてみるのも良策です。経験が乏しければ、最初のうちは効果が得られない場合も多いですが、経験を積むに従い採用につながる求人作成の技術を身につけられます。
また、求人経験のない人材を配置する場合は、採用までの期間を長く見積もっておくことも非常に大切です。効果的な求人が作れるまで人材を育成する心持ちで、長期的な視点で体制を整えましょう。
チームでデータを分析し改善を図る
「運用に知識や経験が必要」という課題は、採用チームで協力して運用する方法も有効です。求人や採用の知見がある人物がいれば任せられますが、求人未経験ばかりであれば運用に悩むことも多くあります。データ分析から課題抽出、修正までのプロセスを明確にして、定期的にチームで相談する場を設ければ、課題解決までをスムーズに行える場合もあるでしょう。
また、データ収集・分析・課題抽出・修正などをタスクに分け、個別に役割を割り振るのもよい方法です。それぞれの特性を活かして作業できるため、作業負担を限定し、精度の高い運用を実施できます。どちらの方法も効果を得るまでには時間がかかる場合もありますが、求人ボックスの課題部分の自社解決が可能です。
求人ボックスの代理店を利用する
「社内に求人の知見がある人材がいない」「もっと早く効果につなげたい」という場合は、求人ボックスの代理店を利用するのもひとつの方法です。求人ボックスの掲載に適した原稿作成やクリック単価や予算の運用など、求人の知識が豊富な専任担当者のサポートが受けられるため、求人の知識がない場合も効果的な運用を行えます。
2025年8月から大新社が求人ボックスの代理店となったため、弊社が提供する採用管理システム(ATS)アットカンパニーでは、求人ボックス広告強化オプションの利用で、求人ボックスへの有料掲載が可能となりました。また、オプションを利用しない場合でも、求人ボックスを含む全6社の求人検索サイトへ、作成した求人を自動連携できるほか、求人作成や運用の作業が負担に感じる場合は、作成から運用までの作業をまるっと任せられます。複数のプランをご用意していますので、自社のリソースや状況に合わせたご利用を、ぜひこの機会にご検討ください。
まとめ:求人ボックスのデメリットを理解し、効果的な運用を
求人ボックスのデメリットを理解し、対策をすることで効果的な運用が可能です。事前に求人掲載から運用までをシミュレーションし、社内リソースを確認のうえ体制の整備を進めましょう。そして採用方針に合わせて採用管理システム(ATS)の利用など、効果的な運用手段の方法を検討することも大切です。今後の採用活動を有利に進めるために、本記事の内容をぜひご参考ください。
また、記事内でご紹介した大新社が提供する採用管理システム(ATS)アットカンパニーは、求人掲載以外にも採用ページや求人ページの作成、応募管理や応募者対応など、採用業務の一元管理ができる採用支援ツールです。ホームページや求人作成の知識がない方でも利用しやすい設計で、近年規模を問わず幅広い企業に利用が広がっています。サービス概要は下記資料よりご確認いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードください。